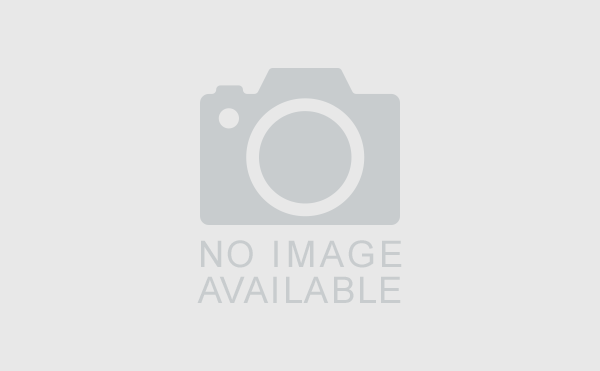石膏デッサンの初講評:ラボルトの稜線
美大受験生にとってデッサンはとても大事である。
上手に描くための早道として筆頭に挙げられるのは『石膏像のデッサン』だ。
美大受験むけのデッサンに使われる石膏像はいくつかあるが、最初に描くのに適しているのはラボルトなのか?美術高校でも初めての石膏像はラボルト(パルテノンのヴィーナスとも呼ばれる)だったが、美術予備校でもそうだった。
今回のラボルト、仕上げは一日。頭だけのデッサンなので、胸像よりも短い時間で仕上げる。
美術予備校での初講評は、『調子はいいんだけど、稜線がね。』だったという。
講評でヘコンだ時には、何を聞いてもたいした返答が返ってこないのだが、今回はまぁまぁだったのか?比較的よくしゃべるようだ。詳しく聞いてみることにした。
石膏像デッサンの調子とは
私「えっと。『調子はいいんだけど、稜線がね。』って、その短い文章の中に二つわからない言葉が出てるんですけど?。」
娘「調子と稜線のこと?じゃ。まずは調子からね。
絵を描いている人にしてみれば、調子と言われれば、ぼんやりわかるんだけどなぁ。うーん。言葉でうまく言えない…すっごく抽象的なものなの。
たとえば、油絵科も彫刻科もデッサンは木炭で描くんだけど、出来上がった絵を並べてみると、調子が全然違うの。
彫刻科は、そのデッサン対象を実際に触った時どんな感じがしたか、それが伝わるように描くことを求められるの。だから、触った感じを二次元で表現しなきゃならないから、彫刻科のデッサンは、たくさん情報が多くて真っ黒になっちゃう。触った感じを表現するので、油絵と違って陰影とかはつけないのね。
あとはね。たとえば…壁にペンキを塗ったとするでしょ。
ペンキ塗りたての壁と、塗ってしばらくたってペンキが乾いた壁と、風化してペンキがはがれてきて汚くなってきた壁と様子が変わってくるでしょ。
調子ってそういう違いを表現したりするの。
あとね。油絵科のデッサンを描く時、光ってとても大事なんだけど、例えばコップを描いたときに、コップのふちにあたる光と、(台に光が反射してコップにあたる)反射光は、同じ光だけど違うように表現するの。
ふちの光はプラスチックケシゴムでギラっと光らせるけど、反射光は影の中に光があって、しっとりと反射している感じを練り消しでだしたりもする。
こういうのも調子にはいるんだと思う。
調子を発展させていって、そのモノの質感をだしていったりもする。
石膏像なら、石膏のつるっとしているけれどもところどころざらついている感じとか、デコボコしてるとことか、トンと叩けば澄んだ音が出るような固いものだ。という感じが調子で出せることが大事なの。
同じ絵の中に違う材質のものが存在している時は、調子を変えて描いたりもする。
調子は、絵を描く人によって出し方が違うので、『そのヒトのスタイルに通じていく。』ものなの。」
ふむ。
……調子ってこういうもの。と一概に言えないということはわかった。
^^;
娘の絵はよく『調子はいいんだけど、形はね。』と言われることが多いのだが、今回は『調子はいいんだけど、稜線はね。』と言われたそうだ。
石膏像デッサンの稜線とは
稜線って、山の稜線とかならわかるけど、絵の稜線ってなに?って聞いてみたら、
すっと手を出して、これで稜線ってわかる?と言われたので、指でなぞると、そこは輪郭だよ。と笑われてしまった。

デッサンにおける稜線というのは、光と影の境目にできるのだ。
「光の世界と影の世界の分かれ目のことなの。稜線をつけると、そこで形に大幅な変化が出ていると表すことができる。それがないと、なだらかにつるーっとしているように見えてしまうの。必要なところに稜線をつけないと、ぼやっと膨張してみえちゃうんだ。」
描く対象を、光の世界と影の世界だけで分けた時にできるラインのことを稜線という。
だから、曲がっているかもしれないけど、一本だけあるはずの稜線。
その稜線を見つけて絵を描くと、よりはっきりした絵がかけるようになるようだ。
画学生が体験している世界は、わからないことだらけだ。
邪魔にならない程度に、ちょっとずつ教えてもらえると嬉しい。
それにしても、山以外に稜線があるとは知らなかったなぁ。